拡張機能「WorkFlowy Images」(&「Gyazo」)を使ってWorkFlowyで画像を扱う
定期的にChromeウェブストアで「WorkFlowy」を検索するマンです。
「WorkFlowy Images」という拡張機能を使ってみたらかなり良かったので紹介。
機能は「画像のURLをWorkFlowyのトピックやノートに貼り付けると画像が表示される」というもの。名前の通りですね( ◠‿◠ )
▼ イメージ
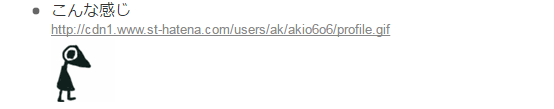
ちなみに短縮されてて拡張子がついてないURLでもMarkdown記法で書けば画像として認識されるっぽい。便利。
URLの画像をその場で表示させるための拡張機能はいくつかあるんだけど、設定不要で何も考えずに使えて、WorkFlowyに限定されているものは他にないと思う。
画像のアップロード先はどうする?
この拡張機能はWorkFlowyに直接アップするわけじゃないので、画像のアップロード先を決める必要がある。
自分の用途や求めることを挙げてくと、
- 扱う画像はスクショが多い
- ブログにアップするかもしれない
- アップロードは簡単にしたい
- スマホからも操作したい
- 基本非公開がいい
って感じ。
その辺を踏まえて、先日記事を書いたScrapboxを開発したNota Inc.の「Gyazo」がいいんじゃないかと考えた。
Gyazoなら、
- 拡張機能でスクショが簡単に撮れて、即URLがクリップボードコピーされる
- Gyazo - Chrome ウェブストア
- URL(+.png)を貼り付ければすぐにWorkFlowyで見られる
- スクショだけじゃなくて画像のドラッグアンドドロップでもアップロード可能
- 保存期間無制限
- 無料や未登録だと過去画像の閲覧に制限があるけど、画像の管理というよりはアップロードしたいだけなので、URLさえ分かっていれば問題なし
- スマホアプリあり
- URLさえ分かれば見られるパターン
と、自分の求める機能をバッチリ満たしている。特にスクショしてすぐにURLがコピーされるのが快適。
■
そんなわけで「Gyazoでアップロードして自動でコピーされたURLをWorkFlowyに貼り付けて拡張子を書き足すと、WorkFlowy Imagesにより自動で画像が表示される」フローができあがった。よし。
HandyFlowyからDueに送るためのスクリプト作った
WorkFlowyには通知がない。
ってことでリマインダーアプリの定番「Due」と連携するスクリプトを書いた。
title=document.title.replace(/- WorkFlowy/,"");
hflink="handyflowy://open?topic="+location.href.split("#/")[1];
url="due://x-callback-url/add?title="+encodeURIComponent(title)+" "+encodeURIComponent(hflink);
open(url);
HandyFlowyでこのスクリプトを実行すると、「ズームしてるトピック名+そのトピックを開くURLスキーム」をリマインダーとして登録する。
で、これ試しながら気づいたんだけど、Dueってタイトルの中に日時が書いてあるとそれを解析して通知時刻を設定してくれるのね。ナイス。
ちなみに点線部をタップすると削除もしてくれる。行き届いてる感。
 HandyFlowy
HandyFlowy
カテゴリ: 仕事効率化, ユーティリティ
 Due 〜 リマインダー、タイマー、アラーム
Due 〜 リマインダー、タイマー、アラーム
カテゴリ: 仕事効率化, ユーティリティ
WorkFlowyのアプリ3種使い分け
WorkFlowyを扱うためのアプリは現在3種類。
公式アプリ・HandyFlowy・MemoFlowy
今んとこすべて使ってる。
こうやってアプリに振り回される感じ、アホかっていう目線もあるにはある(一時期のEvernote界隈とかアレだった)んだけど、それぞれ得意なことが違うから役割も変わってくるのよね。
もちろんどれか1つのアプリで全てまかなえる状態に憧れる気持ちはある。でも無理に1つで何でもやろうとせず、それぞれのアプリでしかできないことによって使い方を合わせるのが自分にはあってるっぽい。まぁ3つはギリ許容範囲でしょう。
■
それぞれの得意分野を挙げてみる(便利だと思う順)
- 公式:オフラインで動作・起動時のロード画面がほぼ無い・画面を広く扱える
- HandyFlowy:拡張機能・エクスポート・ツールバー・(拡張機能含む)スタイル変更・ブックマーク・閲覧モード・URLスキーム・語句登録・2タブ・スワイプカーソル
- MemoFlowy:メモを書くことから始められる・スワイプカーソル・語句登録・1ボタンで送信・URLスキーム・オフライン送信・ツールバー・(ブックマーク)
下2つは若干かぶってるところもあるけど、それぞれ長所はバラバラ。
その辺を考慮して私の場合は、
- さくっと見たい時、オフラインの時 → 公式
- お気に入りのスタイルで弄りたい時、編集やエクスポートなど重めの作業する時 → HandyFlowy
- とりあえず入力したい時 → MemoFlowy
って感じで使い分けてる。
常時HandyFlowy開いてるのであれば公式を使わない選択肢もあり得るけど、それも難しい。いざって時にロード開始されるとかなりストレスだし、たまにキャッシュしておかないと(ロード画面が無いとはいえ)差分取得に時間かかるのでちょくちょく起動しておきたいって思惑もあって、公式は外せない。
自分の環境でもHandyFlowyがオフラインで使えれば公式の役割無くなるんだけど。難しいよなー。
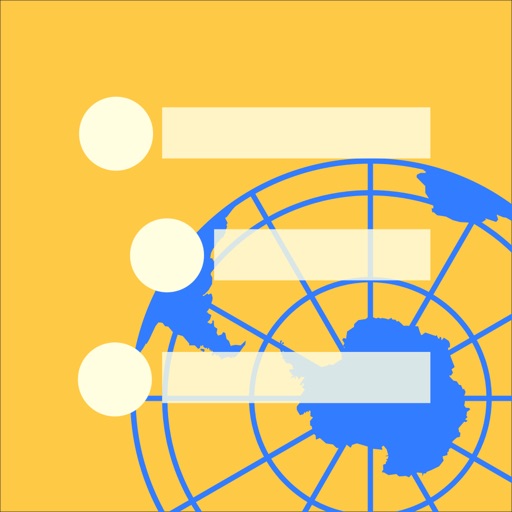

他の人どうだろう?と思って調べてみた
- WorkFlowyの軽量化の先にあるもの – いつもていねいに
- 【定期レビュー】 Memoflowyで収集しHandyflowyで編集する,Workflowyを中心にした2016年6月時点でのブログ執筆のフロー | 知的生活ネットワーク
- MemoFlowyとHandyFlowyとWorkFlowy全部使って文章を書くと、普通に書くよりも楽しい | Sumirexxx
- Android版のMemoFlowyとHandyFlowy | text perforation
やっぱそうなるよね感。
「kanbanflowy」にメモ欄を追加
以前作った「kanbanflowy」に、ちょっとしたメモを書けるスペースを追加してみた。Ver.0.4。

手帳に挟んであるボードに、付箋を貼っつけたイメージ。ちなみに色や幅なんかはstyleタグを弄れば変更できます。
*ブラウザにTampermonkeyやGreasemonkeyをインストールした状態で、以下のリンク先の「Raw」ボタンをクリックするとスクリプトがインストールされます。
機能
とりあえずtextareaをつけただけなので保存はできない。リロードすると文章が消えちゃうんだけど、一時的なメモを残す機能なのでこれでいいと思う。ただ、ページを移動してもロードさえなければ文章は消えないので、WorkFlowy内を移動してるだけなら基本残ってる。
本線と関係ないメモや、あとで他の位置に移動させることが決まっているテキストなどはここに置いとくといいかも。
Make lists, not war. (リストをつくり、育てることの楽しさ)
おそらく高校生の終わりか大学入りたての頃だったと思うが、母に勧められてドミニック・ローホーさんの『シンプルリスト』を読んで以来、アナログ・デジタル問わず「リストをつくる」のが習慣になっている。

- 作者: ドミニック・ローホー
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2015/12/04
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る
本の中で例に挙がっているリストは、いわゆる「女子」ウケしそうなキラキラしたものが多くて「うっ」っとなり、そのリストをつくってみても案の定あんま書けなかったんだけど*1、「リストをつくる習慣」をもてたのはすごくよかった。
なんかあったら「これリストにできるな」って考えるし、発見があったり、気が向いたらリストを見返して追記したり、順番を入れ替えたりしてる。
これがなんか楽しくて非常によい。
言語化しようと思ったら「自分のことがすこし分かるようになった」とか「リスト化した対象についての知識が増えた」とか「時間をおいて対象と向き合う時間をもてる」とかなんだかんだ書けると思うんだけど、「なんか楽しい」ってのがしっくりくる。
▼ 書いててなんか楽しいと思うリストの一部

ふざけ半分でつくったやつが多い(真面目そうな「真実」の第一項目は「冷えたナンはまずい」だったり)けど、こういうのこそ作ってて楽しい。ものが貯まっていく楽しさなのか、並んでるものを観る楽しさなのか、自分の書いたものを読む楽しさなのかは分からないけど、楽しいのは確か。
で、そういう楽しさは、リストを作ってなかったら絶対に味わえてないものだと思う。それがドミニック・ローホーさんの言う“ゆたかな人生”なのかは全然分かんないんだけど、無いよりはあった方が楽しいと言い切れる。
楽しい人生か楽しくない人生だったら楽しい人生の方が_今んとこ_よさそうだと思ってるので、リストをもつ人生かリストをもたない人生だったら、リストをもつ人生を選びたい。
■
WorkFlowyのフッターに書かれてる、
Make lists, not war.
はただのもじりじゃなくて、結構マジだと思う。
*1:今でも続いてるものもある。読んだ本リストとか季節ごとに聴きたい音楽リストとかはたしかこの本きっかけで作り始めたはず。



